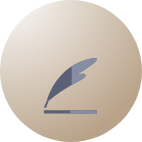Lunch Seminar-「競業避止条項に関する法律規定及び実務」
会社の営業秘密を保護するため、多数の会社は従業員と競業避止条項を締結している。企業と従業員の競業避止条項の有効性について、労働部及び裁判所は既に数多い見解を示したが、法律では終始明確な規定がなく、実務見解も一致ではない。特に、雇用主が従業員に競業避止制限の補償金を支給することを競業避止条項の発効要件とするか否か、するのであれば、どのぐらい支給すべきか、そしていつ支給すべきかを巡って論争は依然多々ある。
労働基準法は2015年12月16日に改正され、第9条の1の第1項にて競業避止条項の関連規定が追加された。第9条の1の第1項によれば、下記規定を満たさない場合、雇用主は従業員と退職後の競業避止契約を締結してはならない:(1)雇用主に保護されるべき正当な営業利益があること;(2)従業員の担当する職位又は職務が雇用主の営業秘密にアクセス又は使用できること;(3)競業避止の期間、地域、営業活動範囲及び就職先が合理的な範囲を超えないこと;(4)従業員が競業行為を従事しないことによって生じた損害に対し、雇用主が合理的な補償を支給すること。
また、労働基準法は退職後の競業避止期間が2年を上回ってはならず、2年を超える場合、2年に短縮すべきであり、且つ雇用主は従業員に競業避止制限の補償金を支給する必要があり、さもなければ、競業避止条項は無効となることを明確に規定した。原則として、補償金の額は従業員が退職した際の平均月収の50パーセントを下回ってはならないが、補償金の額が合理的であるかどうかを判断するにはその他の事項も斟酌しなければならず、また、競業避止制限の補償金は従業員が労働期間中に受領した支給に含まれてはならない。なお、雇用主が競業避止の補償金を支給する期間について、労働基準法施行細則によれば、退職後に一括支給するか、又は月ごとに支給するかを合意しなければならない。
裁判所の実務見解によれば、競業避止条項がある場合、たとえ従業員が自己都合による退職でなくても適用される。しかし、従業員が企業に「不当解雇」された場合も競業避止条項に拘束されるかに関して、現在実務ではまだ明確な見解が見当たらない。
雇用主が従業員と競業避止条項を締結しなかった場合、米国の不可避的開示の法理(Inveitable Disclosure Doctrine)又は台湾営業秘密法第11条の規定を引用して従業員の競合会社への入社を禁止した極僅かな裁判例を除き、従業員の競合会社へ就職を禁止するのは法的にかなり困難である。したがって、会社の営業秘密を保護するため、会社はできる限り会社の営業秘密にアクセスできる従業員と競業避止条項を締結することが望ましい。